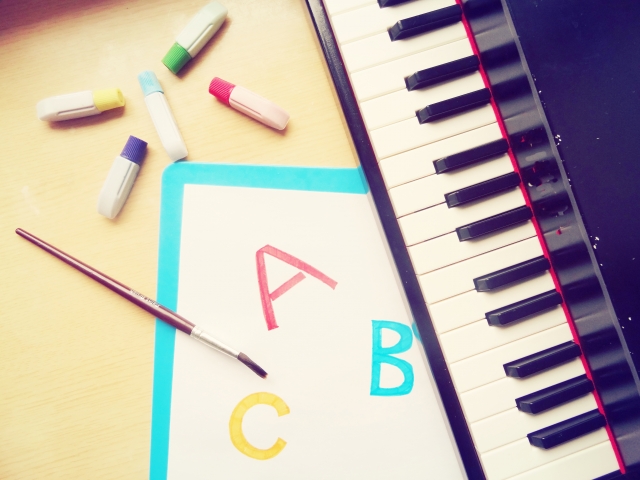過保護とは?過干渉との違いを知って子どもの自己肯定感をUPさせる育児をしよう♪
2017年7月7日 公開
過保護とはいったいどのようなことか説明することができますか?子どものことを思って子育てをしているママのほとんどが過保護でしょう。親世代や祖父母世代では過保護=甘やかしとして良くないことだと思われてきました。本当によくないことなのでしょうか?現在では、過保護は子どもの成長過程でとても大切なことだという専門家もいます。なぜなら過保護とは子どもの自己肯定感を育むことに繋がるからです。しかし過保護を通り越して過干渉になってしまうと、子どもの成長過程に大きな影響を与えます。今回は過保護と過干渉の違いや自己肯定感について解説します!
過保護とは?あなたは過保護?
via pixabay.com
毎日育児を頑張っているママが多いと思います。私も2児のママとして毎日四苦八苦しています。
ママはいつも子どものことを考え、子どもの喜ぶこと、好きなことなど子どもの望みをできる限りかなえてあげたいと思っているでしょう。
そこで気になるのが「過保護」という言葉。
まずは、あなたが過保護なのかチェックしてみましょう!
ママはいつも子どものことを考え、子どもの喜ぶこと、好きなことなど子どもの望みをできる限りかなえてあげたいと思っているでしょう。
そこで気になるのが「過保護」という言葉。
まずは、あなたが過保護なのかチェックしてみましょう!
【過保護チェック】
まずやってしまっていることをチェックしてみましょう!
□ 子どもがやっていることに先回りして手を出してしまう。
□ 子どもが欲しいものは全て買い与えている。
□ 片づけなさいと怒りながら片づけている。
□ 子どもがやりたいことを禁止する。
□ 子どもに「○○したら」など促す。
□ 子どもに身の回りの手伝いをさせない。
あなたはいくつ当てはまりましたか?
ほとんどのママが当てはまる項目が1つはあるのではないでしょうか。
私もいくつか当てはまる項目があります。
この項目にすべて当てはまる場合は、「過保護」かもしれません。
しかし、過保護は悪いことではないので、心配しないでくださいね。
□ 子どもがやっていることに先回りして手を出してしまう。
□ 子どもが欲しいものは全て買い与えている。
□ 片づけなさいと怒りながら片づけている。
□ 子どもがやりたいことを禁止する。
□ 子どもに「○○したら」など促す。
□ 子どもに身の回りの手伝いをさせない。
あなたはいくつ当てはまりましたか?
ほとんどのママが当てはまる項目が1つはあるのではないでしょうか。
私もいくつか当てはまる項目があります。
この項目にすべて当てはまる場合は、「過保護」かもしれません。
しかし、過保護は悪いことではないので、心配しないでくださいね。
過保護=良くないことって本当?
via pixabay.com
過保護に育てすぎると、「甘えん坊になる」「甘やかしすぎる」と良くないことと思っているママも多いのではないでしょうか?
確かに、「過保護すぎる」と子どもの人格形成に影響が出てしまう場合があるようですが、過保護に育てることは悪いことではありません。
むしろ自分の子どもを過保護に育ててしまうママが多いはず。かわいい我が子には痛い思いや寂しい思いなど不自由なく過ごしてほしいと願い行動してしまいます。
昔は、過保護に育てると子どもに悪影響が出るとして良くないこととされていましたが、現在は少し違う意見も出てきています。
それが、過保護でも良いという考えです。
現在は、反抗期を迎えずに成長してしまう子どもが多くなってきているようです。
それが過保護に育てたからと思われがちですが、それは違います。
過保護に育てることは、子どもの存在を認めてあげることに繋がるので、子どもの自己肯定感が育つとされています。
自己肯定感が育つと、自立も早くなると言われています。
また、自己肯定感が育つと自分に自信を持つことができるようになるので、失敗を恐れずにチャレンジする精神も育まれていくことがあります。
確かに、「過保護すぎる」と子どもの人格形成に影響が出てしまう場合があるようですが、過保護に育てることは悪いことではありません。
むしろ自分の子どもを過保護に育ててしまうママが多いはず。かわいい我が子には痛い思いや寂しい思いなど不自由なく過ごしてほしいと願い行動してしまいます。
昔は、過保護に育てると子どもに悪影響が出るとして良くないこととされていましたが、現在は少し違う意見も出てきています。
それが、過保護でも良いという考えです。
現在は、反抗期を迎えずに成長してしまう子どもが多くなってきているようです。
それが過保護に育てたからと思われがちですが、それは違います。
過保護に育てることは、子どもの存在を認めてあげることに繋がるので、子どもの自己肯定感が育つとされています。
自己肯定感が育つと、自立も早くなると言われています。
また、自己肯定感が育つと自分に自信を持つことができるようになるので、失敗を恐れずにチャレンジする精神も育まれていくことがあります。
自己肯定感とは?
「自己肯定感」という言葉を聞いたことはありませんか?
最近育児書などに出てくるので見たり聞いたりしたことがあるママが多いと思います。
簡単に言うと自己肯定感は、自己を肯定することつまり「自分は存在してもいいんだ」と感じることです。
自己肯定感で大切なことは、子ども自身が「自分は居ても良い存在」と感じることです。
子どもがそう感じるためには、親やその子どもに関わる人がその子の存在を受け入れることが大切です。
だからこそ、過保護は育児には大切になってきます。
子どものすべてを受け入れ、愛情を注ぐことが自己肯定感を育んでいくようです。
しかし「過保護すぎる」のは良くないことです。そのうち過干渉になってしまう恐れがあるので、気を付けたほうがよさそうです。
最近育児書などに出てくるので見たり聞いたりしたことがあるママが多いと思います。
簡単に言うと自己肯定感は、自己を肯定することつまり「自分は存在してもいいんだ」と感じることです。
自己肯定感で大切なことは、子ども自身が「自分は居ても良い存在」と感じることです。
子どもがそう感じるためには、親やその子どもに関わる人がその子の存在を受け入れることが大切です。
だからこそ、過保護は育児には大切になってきます。
子どものすべてを受け入れ、愛情を注ぐことが自己肯定感を育んでいくようです。
しかし「過保護すぎる」のは良くないことです。そのうち過干渉になってしまう恐れがあるので、気を付けたほうがよさそうです。
「甘やかす育児」と「甘えさせる育児」は違う!子どもの自立心を育む子育てはどっち?! – ikumama

「甘やかす」と「甘えさせる」って何が違うか分かりますか?各家庭によって、子どものしつけに対する考え方は違いますが、子どもにとってどちらがいいでしょうか?同じ「甘え」でも、それぞれ子どもに与える影響は違います。甘やかし育児、甘えさせる育児、それぞれの特徴をまとめました。
過保護より恐ろしい「過干渉」
via pixabay.com
過保護と過干渉は違います。過保護は育児をする上で大切ですが、過干渉は子どもの発達に影響を与える可能性があります。
過干渉と過干渉は違うものですが、子どもが成長していくにつれて、過保護が過干渉になってしまうこともあります。
まずは自分が過干渉になっていないかチェックしてみましょう。
過干渉と過干渉は違うものですが、子どもが成長していくにつれて、過保護が過干渉になってしまうこともあります。
まずは自分が過干渉になっていないかチェックしてみましょう。
【過干渉チェック】
□ スマホのLINEやメールなどチェックする。
□ 友だち付き合いに口を出す。
□ 子どもの1日のスケジュールを把握している。(学校に行っていれば時間割を知っている)
□ 進路など一定以上でなければ口を出す。
□ ほめることが少なく、怒ることが多い。
いかがですか?
少しでも当てはまる方は、過干渉になりつつあるかもしれません。
□ 友だち付き合いに口を出す。
□ 子どもの1日のスケジュールを把握している。(学校に行っていれば時間割を知っている)
□ 進路など一定以上でなければ口を出す。
□ ほめることが少なく、怒ることが多い。
いかがですか?
少しでも当てはまる方は、過干渉になりつつあるかもしれません。
過保護と過干渉との違いは?
via pixabay.com
よく過干渉と過保護が同じもののようにとらえてしまいがちですが、厳密にいうと違うものです。
過保護は「子どもが望んでいることをやってあげる」ことだとしたら、過干渉は「子どもが望んでいないことをやってあげる」ことになります。
「子どものために」と口癖になっているママは過干渉になってしまっているかもしれません。
「子どもの将来のために塾に行かせる」、「子どもが良い暮らしができるようにいい学校、いい大学に行かせる」など、子どもの将来を心配するあまり、子どもの進路を決めてはいませんか?
どの親でも子どもの将来は心配です。
しかし、子どもが望んでいないのに進路を決めたり、身の回りのことを親が決めてしまうと子どもの自立の芽を摘んでしまうかもしれません。
過保護は「子どもが望んでいることをやってあげる」ことだとしたら、過干渉は「子どもが望んでいないことをやってあげる」ことになります。
「子どものために」と口癖になっているママは過干渉になってしまっているかもしれません。
「子どもの将来のために塾に行かせる」、「子どもが良い暮らしができるようにいい学校、いい大学に行かせる」など、子どもの将来を心配するあまり、子どもの進路を決めてはいませんか?
どの親でも子どもの将来は心配です。
しかし、子どもが望んでいないのに進路を決めたり、身の回りのことを親が決めてしまうと子どもの自立の芽を摘んでしまうかもしれません。
過保護でも「見守る」ことを忘れない
via pixabay.com
過保護でもやりすぎはNGです。
子どもの自己肯定感をはぐくむために過保護であっても良いですが、やりすぎは過干渉になってしまう恐れがあるので、気を付けてくださいね。
公園の遊具で子どもを遊ばせると怪我をしてしまう恐れがあるので、遊具で遊ばせないというママもいるかもしれません。
しかし、遊具で遊んで怪我をしたとき子どもはなぜ怪我をしたのか考えることができます。
また、次も同じ失敗をしないように工夫をすることを覚えます。
人間はこうして学習し成長していきます。
だから、過保護でも「見守る」ことが大切。子どもにいろいろな経験をさせて、たくさんの刺激を受けさせてくださいね。
ただし、大怪我をしては子どものあらゆる可能性をつぶしてしまう恐れがあるので気を付けてくださいね。
さじ加減は親自身の判断になりますが、見守ることを大切にしながら、子育てをたのしんでくださいね。
子どもの自己肯定感をはぐくむために過保護であっても良いですが、やりすぎは過干渉になってしまう恐れがあるので、気を付けてくださいね。
公園の遊具で子どもを遊ばせると怪我をしてしまう恐れがあるので、遊具で遊ばせないというママもいるかもしれません。
しかし、遊具で遊んで怪我をしたとき子どもはなぜ怪我をしたのか考えることができます。
また、次も同じ失敗をしないように工夫をすることを覚えます。
人間はこうして学習し成長していきます。
だから、過保護でも「見守る」ことが大切。子どもにいろいろな経験をさせて、たくさんの刺激を受けさせてくださいね。
ただし、大怪我をしては子どものあらゆる可能性をつぶしてしまう恐れがあるので気を付けてくださいね。
さじ加減は親自身の判断になりますが、見守ることを大切にしながら、子育てをたのしんでくださいね。
過保護で自己肯定感UP!
via pixabay.com
最近、反抗期を迎えない子どもが増えているようですが、そのひとつの原因として過干渉や自己肯定感が低いことが挙げられるようです。
自己肯定感が低いと、自分に自信がないことに繋がるので物事でも自分の意志で決めることができず、親の判断を仰いだりしなければ決めることができないということになってしまいます。
「くそばばあ!」といわれるのが嫌だと誰でも思いますが、子どもが親に反抗するということは、自分の意志を持ち、外に出すことができるようになってきたということで素晴らしい成長です。
それに反抗期は、一時的なことなのでひどい言葉を言われてもグッとこらえて成長を見守りましょう。
また、反抗してくるということは「自分のことを受け止めてくれる」という安心が子どもの中にあるからだそうです。
それこそ自己肯定感が高いからこそ反抗期が来るのかもしれませんね。
自己肯定感が低いと、自分に自信がないことに繋がるので物事でも自分の意志で決めることができず、親の判断を仰いだりしなければ決めることができないということになってしまいます。
「くそばばあ!」といわれるのが嫌だと誰でも思いますが、子どもが親に反抗するということは、自分の意志を持ち、外に出すことができるようになってきたということで素晴らしい成長です。
それに反抗期は、一時的なことなのでひどい言葉を言われてもグッとこらえて成長を見守りましょう。
また、反抗してくるということは「自分のことを受け止めてくれる」という安心が子どもの中にあるからだそうです。
それこそ自己肯定感が高いからこそ反抗期が来るのかもしれませんね。
過保護でも楽しく育児をすることを忘れずに♪
via pixabay.com
過保護に育てると自分の親世代や祖父母世代にはよく思われないかもしれません。
しかし、過保護が悪いというわけではありません。
むしろ過保護は大切という専門家もいます。
過保護に育てるかは、育児をしているママとパパが決めることではないでしょうか。
自分の子どもがかわいいと思い不自由させたくないと感じることは、親なら当たり前ではないでしょうか。
何が良くて何が悪いのか判断は難しいですが、その子を一番大切にできるのはママとパパです。
過干渉は子どものその後に影響を与えてきますが、適度な過保護であれば良いのではないでしょうか?
今回は過保護についてでしたが、最も大切なのはママが笑顔に育児を楽しむことです。
笑顔を忘れずに、子育てを楽しんでくださいね♪
しかし、過保護が悪いというわけではありません。
むしろ過保護は大切という専門家もいます。
過保護に育てるかは、育児をしているママとパパが決めることではないでしょうか。
自分の子どもがかわいいと思い不自由させたくないと感じることは、親なら当たり前ではないでしょうか。
何が良くて何が悪いのか判断は難しいですが、その子を一番大切にできるのはママとパパです。
過干渉は子どものその後に影響を与えてきますが、適度な過保護であれば良いのではないでしょうか?
今回は過保護についてでしたが、最も大切なのはママが笑顔に育児を楽しむことです。
笑顔を忘れずに、子育てを楽しんでくださいね♪