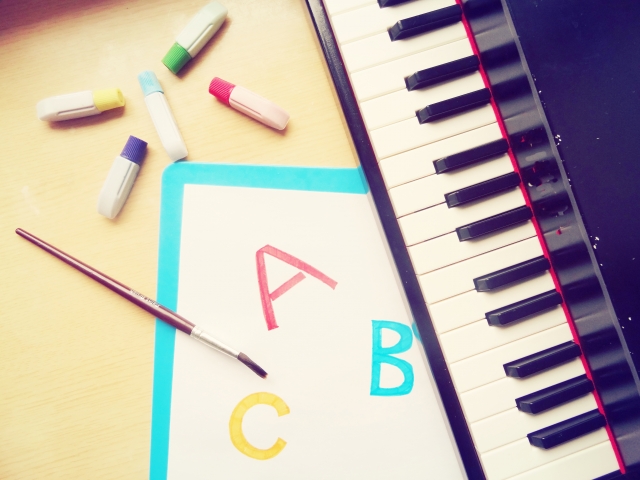子どもの病気は季節に合わせて変わる!生活や気候の変化に合わせて対策と予防を!
2017年3月18日 公開
子どもは色々な病気になってしまう
via www.pakutaso.com
子どもはどうしてもちょっとした事でも病気を引き起こしてしまうほど抵抗力が育っていません。気が付いたときには症状が進んでしまう事が多く、普段との様子の違いをしっかりと見極める必要があります。
また、子供には多い熱性けいれんを引き起こしてしまう感染症も多くあります。熱性けいれんについても対処法を知っているのと知らないのでは大きな差が出てきてしまいます。
今回はそんな子どもの季節の病気とポイント、予防について一緒に確認していきましょう。
また、子供には多い熱性けいれんを引き起こしてしまう感染症も多くあります。熱性けいれんについても対処法を知っているのと知らないのでは大きな差が出てきてしまいます。
今回はそんな子どもの季節の病気とポイント、予防について一緒に確認していきましょう。
季節によって流行が違う
via www.pakutaso.com
子どもの病気の多くは感染症とされています。子どもの突然の発熱や発疹は不安になってしまい、困ってしまう事もしばしばありますよね。感染症は季節によって様々なものが流行します。
この流行を事前に知っておく事で落ち着いて対処が出来るので流行というものを知っておくのは子どもの為にもなります。
春に流行するもの、夏に流行するもの、秋に流行するもの、冬に流行するものだけではなく、保育園や学校の休みに関連する事も少なくありません。まずは季節によるものから確認していきましょう。
この流行を事前に知っておく事で落ち着いて対処が出来るので流行というものを知っておくのは子どもの為にもなります。
春に流行するもの、夏に流行するもの、秋に流行するもの、冬に流行するものだけではなく、保育園や学校の休みに関連する事も少なくありません。まずは季節によるものから確認していきましょう。
春に多い子どもの病気
via www.pakutaso.com
春(4月~5月ごろ)から流行する病気は少ないですが、入園や進級などの生活の変化によって子どもは体調を崩しやすい特徴があります。鼻水・発熱などをしっかりと見逃さないようにしましょう。
春に多い病気として
・溶連菌感染症
・インフルエンザ
・感染性胃腸炎
・水ぼうそう
などがあげられます。冬から続いている感染症が多くあるので気の緩みから感染症を引き起こしやすいので注意が必要です。
春に多い病気として
・溶連菌感染症
・インフルエンザ
・感染性胃腸炎
・水ぼうそう
などがあげられます。冬から続いている感染症が多くあるので気の緩みから感染症を引き起こしやすいので注意が必要です。
特に注意しておきたい溶連菌感染症
高熱と喉の痛みやイチゴ舌が特徴的なのが溶連菌感染症です。新生活が始まる春先などに特に多く、風邪に似た症状が出てきます。全身に赤いブツブツをが見られることもあります。
溶連菌感染症の場合は抗生物質を飲みきるまできちんと治療する必要があります。また、合併症が現れる危険性もあるので抗生物質を飲みきった後でも一度、小児科に受診をして確認してもらう事をお勧めします。
溶連菌感染症の場合は抗生物質を飲みきるまできちんと治療する必要があります。また、合併症が現れる危険性もあるので抗生物質を飲みきった後でも一度、小児科に受診をして確認してもらう事をお勧めします。
夏に多い子どもの病気
via www.pakutaso.com
夏(6月~8月ごろ)から流行する病気は発疹や口内炎を伴う病気が多いので全身の観察に注意しながら過ごしていくようにしましょう。
夏に多い病気として
・手足口病
・ヘルパンギーナ
・プール熱
・アデノウイルス
・とびひ
等があります。また、春に流行った感染症が残っている場合があるので予防を継続しながら脱水などに注意して過ごしましょう。
夏に多い病気として
・手足口病
・ヘルパンギーナ
・プール熱
・アデノウイルス
・とびひ
等があります。また、春に流行った感染症が残っている場合があるので予防を継続しながら脱水などに注意して過ごしましょう。
特に注意しておきたいプール熱
アデノウイルスが原因によって引き起こされる感染症で、プールの水から感染します。幼稚園児や小学生はプールでの感染が多くありますが、他にも咳やくしゃみによっても感染が確認されています。
プールに入る前、後 にしっかりと体、手、目を洗っておく事やタオルや洗面器、食器を共有しないという事が大切です。出来る事ならば洗濯物も別にすると予防に効果的です。
プールに入る前、後 にしっかりと体、手、目を洗っておく事やタオルや洗面器、食器を共有しないという事が大切です。出来る事ならば洗濯物も別にすると予防に効果的です。
秋に多い子どもの病気
via www.pakutaso.com
秋(9月~11月ごろ)から流行するものは季節の変化に反応して気管支ぜんそくが悪化してしまう季節とされています。感染症の予防が重要なポイントとなっているので気を付けましょう。
秋に多い病気として
・RSウイルス感染症
・ノロウイルス
・マイコプラズマ肺炎
・ノロウイルス
などが考えられます。これらは冬になるともっと活発的に活動するウイルスなので出来る事ならば秋のうちからしっかりと対策をしておくのが良いですね。
秋に多い病気として
・RSウイルス感染症
・ノロウイルス
・マイコプラズマ肺炎
・ノロウイルス
などが考えられます。これらは冬になるともっと活発的に活動するウイルスなので出来る事ならば秋のうちからしっかりと対策をしておくのが良いですね。
特に注意しておきたいノロウイルス
子どもの場合は学校や幼稚園、保育園からノロウイルスに感染する事が多くあります。自宅にもってかえって家族で感染してしまう事があるほどの強力な感染力を持っています。
腹痛、下痢、嘔吐、発熱といった症状が子供に出ている場合にはノロウイルスの可能性を考えましょう。ノロウイルスは大人の場合と違って回復が遅く、症状が軽いように見えてしまいます。嘔吐の症状が顕著に出るケースが多いので判断の材料として覚えて予防、治療を徹底しましょう。
腹痛、下痢、嘔吐、発熱といった症状が子供に出ている場合にはノロウイルスの可能性を考えましょう。ノロウイルスは大人の場合と違って回復が遅く、症状が軽いように見えてしまいます。嘔吐の症状が顕著に出るケースが多いので判断の材料として覚えて予防、治療を徹底しましょう。
冬に多い子どもの病気
via www.pakutaso.com
冬(12月~3月ごろ)から流行するものはインフルエンザなどの強力な感染症が多いです。ノロやロタといった嘔吐や下痢を引き起こすものが多いので注意が必要です。
冬に多い病気として
・インフルエンザ
・感染性胃腸炎
・みずぼうそう
・溶連菌感染症
・RSウイルス感染症
といった強い感染力をもったウイルスが活発に活動します。部屋の乾燥などで活動力が上がってしまうので出来るだけ加湿をしてしっかりと予防をしておくのが大切です。
冬に多い病気として
・インフルエンザ
・感染性胃腸炎
・みずぼうそう
・溶連菌感染症
・RSウイルス感染症
といった強い感染力をもったウイルスが活発に活動します。部屋の乾燥などで活動力が上がってしまうので出来るだけ加湿をしてしっかりと予防をしておくのが大切です。
特に注意しておきたいインフルエンザ
冬の乾燥する時期にはインフルエンザが流行します。予防接種がありますが、このインフルエンザは毎回型を変えてやってくるので予防接種を受けている場合であっても油断はしないようにしましょう。
症状がインフルエンザの型によって変わってくる点も注意が必要です。特に2~4歳頃の子供はインフルエンザにかかりやすく、高熱が続きます。後述する熱性けいれんが引き起こされる事もあり様子をしっかりと観察する必要があります。
38度以上の発熱の有無、インフルエンザが流行していないか、関節や筋肉痛、倦怠感や疲労感、頭痛などがないかなど確認できる年齢であれば確認しておきましょう。
症状がインフルエンザの型によって変わってくる点も注意が必要です。特に2~4歳頃の子供はインフルエンザにかかりやすく、高熱が続きます。後述する熱性けいれんが引き起こされる事もあり様子をしっかりと観察する必要があります。
38度以上の発熱の有無、インフルエンザが流行していないか、関節や筋肉痛、倦怠感や疲労感、頭痛などがないかなど確認できる年齢であれば確認しておきましょう。
子どもの集団生活が始まったときは要注意
via www.pakutaso.com
子どもの集団生活が始まるころはまだ感染症に対する抵抗力が弱いので様々な病原体にさらされる事になります。保育園などに通う子よりも通わない子の方が風邪などの感染症にかかり難いという統計があります。
感染症の中には出席停止になってしまうものもあるので予防出来る事が可能なものは出来るだけしておきましょう。
ちなみに1歳から3歳くらいまでは年間に10回ほど風邪をひくといわれています。幼い頃は体力も抵抗力もあまりないので興奮しただけでも発熱を引き起こす事があります。体調を崩しやすくなるので集団生活が始まったらしっかりと子どもの様子を観察するようにしてあげてくださいね!
感染症の中には出席停止になってしまうものもあるので予防出来る事が可能なものは出来るだけしておきましょう。
ちなみに1歳から3歳くらいまでは年間に10回ほど風邪をひくといわれています。幼い頃は体力も抵抗力もあまりないので興奮しただけでも発熱を引き起こす事があります。体調を崩しやすくなるので集団生活が始まったらしっかりと子どもの様子を観察するようにしてあげてくださいね!
高熱を伴う子どもの熱性けいれんに注意して
via www.pakutaso.com
熱性けいれんとは、発熱に伴って引き起こされるけいれんの事です。発熱は38℃以上で
生後6ヶ月から6歳くらいまでの乳幼児に多くみられる症状です。場合によっては意識障害を引き起こす事があります。
痙攣は突然引き起こされるので、意識障害とよばれる呼びかけへの反応がなくなる、顔色がわるくなるというものが出てきます。初めてみる場合にはパニックになってしまうケースも少なくありません。
しかし、この症状はよく引き起こされるもので、珍しいものではなく後遺症がのこったり死亡してしまうことはほとんどないのでまずは落ち着いて対処しましょう。
痙攣は突然引き起こされるので、意識障害とよばれる呼びかけへの反応がなくなる、顔色がわるくなるというものが出てきます。初めてみる場合にはパニックになってしまうケースも少なくありません。
しかし、この症状はよく引き起こされるもので、珍しいものではなく後遺症がのこったり死亡してしまうことはほとんどないのでまずは落ち着いて対処しましょう。
大声で名前を呼んだり、身体を揺すったりする(刺激となり、けいれんが長引く場合があります)
舌を噛まないように口の中に物を入れる(熱性けいれんで舌を噛むことはほとんどありません。また、噛む力はかなり強いため、2次損傷の恐れがあります)
少なくとも、このような事を避ければ問題ありません。してはいけないことなのでこれは覚えておきましょう。
症状の多くは2~3分程度で治ります。何事もなかったかのようにもどるので救急車を呼ぶ前にしっかりと様子を見てからにしましょう。しかし、呼ばなければならないケースもあります。
5分以上の発作が続く、発作がおさまっても意識の戻りがわるい、顔色がわるい場合には救急車で対応してもらいましょう。
5分以上の発作が続く、発作がおさまっても意識の戻りがわるい、顔色がわるい場合には救急車で対応してもらいましょう。
徹底した予防をしていこう
via www.pakutaso.com
まず出来る事と言えば手を洗うことです。とても簡単ですが、出来ていない場合が多くあり、きちんと行う事で感染症の予防になります。手を洗ってきなさいといっても綺麗に洗えているかの確信はありません。徹底するならば石鹸などの準備としっかりと洗えるように細かく教えながらたのしんで身に着けてもらいましょう。
また、とても簡単な事ですが飛沫感染や空気感染を防ぐためにマスクの着用とうがいの励行をしましょう。体に抵抗力、免疫力があればウイルスが入っても問題ありませんが、子どもの頃はどうしても弱いので一度入ってしまうだけでも感染する可能性があります。まずは入らないようにする意識が大切です。
また、とても簡単な事ですが飛沫感染や空気感染を防ぐためにマスクの着用とうがいの励行をしましょう。体に抵抗力、免疫力があればウイルスが入っても問題ありませんが、子どもの頃はどうしても弱いので一度入ってしまうだけでも感染する可能性があります。まずは入らないようにする意識が大切です。
予防接種には、ヒブ、四種混合、BCG、MR、ロタウイルス、インフルエンザなど多くの種類があり、それぞれ接種する回数なども違います。予防接種のスケジュールをかかりつけ医と相談しておくと、接種のタイミングを逃すこともないですね。
予防接種なども有効的に使っていきましょう!
正しい手洗い・うがいを覚えて!
正しい手洗いの方法は
1.指輪や時計などを外す
2.流水で手を洗う
3.石鹸などでしっかり泡立てる
4.手のひら、手の甲をこすり、指の間は両手を組むようにして洗います
5.親指は反対の手でねじるようにキレイにしていきましょう
6.指先、爪の間は手のひらの上でこすります
7.手首も反対の手でねじるように洗います
8.流水でせっけんと汚れを落とします
9.清潔な乾いたタオルで水分をしっかりとれば終了
簡単な事ですが以外と出来ていないので今一度、お子様と一緒に楽しみながら確認してみてください。
次に正しいうがいの方法は
1.うがい前に必ず手を洗う
2.うがい前に口を数回ゆすぐ
3.「おー」の発音でうがいをする
4.液体が冷たくなったら吐きだす
うがいは必ず1度だけではなく最低3回以上行う事で効果が出るので意識して行ってみてくださいね。
1.指輪や時計などを外す
2.流水で手を洗う
3.石鹸などでしっかり泡立てる
4.手のひら、手の甲をこすり、指の間は両手を組むようにして洗います
5.親指は反対の手でねじるようにキレイにしていきましょう
6.指先、爪の間は手のひらの上でこすります
7.手首も反対の手でねじるように洗います
8.流水でせっけんと汚れを落とします
9.清潔な乾いたタオルで水分をしっかりとれば終了
簡単な事ですが以外と出来ていないので今一度、お子様と一緒に楽しみながら確認してみてください。
次に正しいうがいの方法は
1.うがい前に必ず手を洗う
2.うがい前に口を数回ゆすぐ
3.「おー」の発音でうがいをする
4.液体が冷たくなったら吐きだす
うがいは必ず1度だけではなく最低3回以上行う事で効果が出るので意識して行ってみてくださいね。
まとめ
via www.pakutaso.com
いかがでしたでしょうか。
子どもは季節に合わせて様々な病気になります。普段から予防をしっかりとしておかないと危険な状態になる事があります。また、感染力が強いものもあるので注意して過ごすようにしましょう。子供の様子をしっかりと確認して、元気があるか、異変がないかをしっかりとチェックして予防に努めましょうね。
]]>
子どもは季節に合わせて様々な病気になります。普段から予防をしっかりとしておかないと危険な状態になる事があります。また、感染力が強いものもあるので注意して過ごすようにしましょう。子供の様子をしっかりと確認して、元気があるか、異変がないかをしっかりとチェックして予防に努めましょうね。