
端午の節句は何を食べる?おすすめレシピ10選!由来やお祝いの仕方についても詳しくご紹介♪
2019年2月18日 公開
男の子の健やかな成長を祝う「端午の節句」。 お祝いする際の食事は何を食べると縁起が良いのかご存知ですか? 柏餅やたけのこだけでなく、他にも昔から端午の節句に好んで食べられていた食材があるんですよ♪しかも、その1つ1つにはきちんとした意味があるんです! そこで今回は、端午の節句に食べると良い食材とその意味についてご紹介。さらに、子供が喜ぶ端午の節句のお祝いレシピについてもまとめました。 他にも端午の節句の由来や鯉のぼりや鎧兜を飾る日についてなど、正しい知識やマナーもご紹介しています。子供と一緒に飾り付けをしながら、日本の伝統行事について学びましょう♡
端午の節句とは?
via pixabay.com
そもそも「端午の節句」とはどのような行事かご存知ですか?
3月3日「桃の節句」が女の子の成長を祝う行事であるとするならば、5月5日「端午の節句」は男の子の成長を祝う行事です。
とはいえ、男兄弟がいなかったご家庭で育ったママの中には、いまいちどのようなことをしてお祝いして良いのか分からないものですよね。
そこで今回は、端午の節句についていろいろと調べてみました!
男の子がいるママさんは、お祝いする際の参考にご覧ください。
3月3日「桃の節句」が女の子の成長を祝う行事であるとするならば、5月5日「端午の節句」は男の子の成長を祝う行事です。
とはいえ、男兄弟がいなかったご家庭で育ったママの中には、いまいちどのようなことをしてお祝いして良いのか分からないものですよね。
そこで今回は、端午の節句についていろいろと調べてみました!
男の子がいるママさんは、お祝いする際の参考にご覧ください。
おしゃれな室内用鯉のぼり人気8選♡賃貸やマンションでもコンパクトに飾ってお祝いしよう♪ – ikumama

室内に飾る鯉のぼりの人気が近年高まっています。お庭に大きな鯉のぼりを飾るよりも、室内なら気軽に飾ることができますよね。そんな室内用の鯉のぼりには、どんな種類があるのでしょうか?こちらの記事では◎バリエーションが豊富な室内用鯉のぼり◎場所を選ばない室内用鯉のぼり◎意外性でインパクトのある室内用鯉のぼりなどをご紹介いたします。せっかく室内に飾るなら、記念に写真に撮るのを想定して選びたいですよね。写真映えするカラフルな鯉のぼりや、パーティー感の出る鯉のぼりをピックアップしてご紹介していきます!
端午の節句の由来は?
via www.photo-ac.com
日本の伝統的な行事の1つのように思われた方も多いでしょうが、実は端午の節句は中国から伝来してきた習わしと言われています。
諸説あるのですが、古代中国では5月は『物忌みの月』と言われており、厄払いが行われていたのだそうです。
もともとは「端午」とは、5月のはじめの「午(うま)の日」を指していて、「午」と「五」の音が同じと言うことから5月5日に厄払いをする風習が定着したと言います。
それから日本に伝わり、鎌倉時代に入ると、厄除けに使われる菖蒲と、武道を重んじる意味の「尚武(しょうぶ)」の語呂合わせにより、「5月5日=尚武の日」として盛んにお祝いされるようになったそうです。
その後江戸時代に入ると、端午の節句となり、男の子が無事に成長することを願ってお祝いする行事へと形を変えて庶民の間で広がったとされています。
諸説あるのですが、古代中国では5月は『物忌みの月』と言われており、厄払いが行われていたのだそうです。
もともとは「端午」とは、5月のはじめの「午(うま)の日」を指していて、「午」と「五」の音が同じと言うことから5月5日に厄払いをする風習が定着したと言います。
それから日本に伝わり、鎌倉時代に入ると、厄除けに使われる菖蒲と、武道を重んじる意味の「尚武(しょうぶ)」の語呂合わせにより、「5月5日=尚武の日」として盛んにお祝いされるようになったそうです。
その後江戸時代に入ると、端午の節句となり、男の子が無事に成長することを願ってお祝いする行事へと形を変えて庶民の間で広がったとされています。
【こどもの日】手作り鯉のぼり特集♡動画・無料型紙・キットで子供と一緒に楽しく工作しよう! – ikumama

鯉のぼりを手作りしてみたいけど難しそう!そんな方におすすめの簡単な作り方をご紹介します♡動画・無料型紙・キットがあれば子供と一緒に楽しく鯉のぼりを手作りすることができますよ♪ 手作り鯉のぼりなら、作る瞬間から楽しむことができるのでぜひ挑戦してみませんか?
端午の節句は何を食べてお祝いするの?
桃の節句だと「桜餅」「ちらし寿司」「はまぐりのお吸い物」などが定番メニューですが、端午の節句はどのようなものを食べたら良いのでしょうか?
◆柏餅
桃の節句と言えば、ピンク色の可愛らしい桜餅を食べますが、端午の節句では柏餅を食べるのが習慣です。
これにもちゃんとした意味があります。
柏の葉っぱは、新芽が出ないと古い芽が落ちないことから、『子供が出来るまでは親は死なない』と言われ、子孫繁栄を意味し、端午の節句にふさわしい縁起の良い食べ物となったそうです。
これにもちゃんとした意味があります。
柏の葉っぱは、新芽が出ないと古い芽が落ちないことから、『子供が出来るまでは親は死なない』と言われ、子孫繁栄を意味し、端午の節句にふさわしい縁起の良い食べ物となったそうです。
◆ちまき
ちまきというと、笹の葉でもち米を包んで蒸した食べ物を言いますが、昔は「茅(ちがや)」という葉で巻かれていたのだそうです。この茅の葉は、古来中国では繁殖力が強く、神霊が宿るため邪気を払ってくれる植物とされてました。
このため、端午の節句に茅の葉でもち米を包んで食べる習慣が生まれたと言われています。
ほかにも、このちまきの形状が毒蛇に似ていることから、邪気を払うと信じられていたという説もあります。
このため、端午の節句に茅の葉でもち米を包んで食べる習慣が生まれたと言われています。
ほかにも、このちまきの形状が毒蛇に似ていることから、邪気を払うと信じられていたという説もあります。
◆ブリの照り焼き
ブリは、大きくなるに従い、名前が変わる出生魚。そのことにちなんで、「子供の出世を願う」という意味合いで、端午の節句に好んで食べられるようになりました。
◆カツオのたたき
カツオは、「勝男」という語呂合わせから、「勝つ」=縁起が良いとされ、ちょうどこの時期に旬を迎えるカツオを端午の節句に食べるようになったと言われています。
◆たけのこの煮物
たけのこは、すくすく真っすぐ伸びて大きく育つことから、子供の成長を願い、端午の節句に食べられるようになりました。ちょうど5月が旬の食べ物ということもあり、昔は煮物にして食べる家庭が多かったそうです。
現在は、たけのこご飯にする家庭が多いかもしれませんね。
現在は、たけのこご飯にする家庭が多いかもしれませんね。
端午の節句におすすめ♡子供が喜ぶ簡単・レシピ集
via www.photo-ac.com
端午の節句の食べ物は、これまでご紹介したとおり、カツオやブリ、たけのこ、柏餅などでしたが、現在ではこれに限らず、ちらし寿司や手巻き寿司、鯉のぼりをモチーフにしたスイーツなど子供が好きなメニューでお祝いするのが主流です。
あまり型にはまらず、難しく考えずに子供が楽しく食事できるようなメニューを考えるといいかもしれませんね。以下に、見ているだけでワクワクしちゃう♡おすすめのレシピをご紹介します。
あまり型にはまらず、難しく考えずに子供が楽しく食事できるようなメニューを考えるといいかもしれませんね。以下に、見ているだけでワクワクしちゃう♡おすすめのレシピをご紹介します。
◆端午の節句・こどもの日 たけのことわかめのお吸い物(若竹汁) by toco* 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「端午の節句・こどもの日 たけのことわかめのお吸い物(若竹汁)」端午の節句・こどもの日のたけのこ料理。たけのこのお吸い物。たけのこの水煮と顆粒昆布だしで簡単、時短。 材料:たけのこ(水煮) 穂先の部分+α 、わかめ(塩蔵わかめ)、水..
◆鯉のぼり巻き寿司♪子どもの日☆端午の節句 by YOCCHIMAMA 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「鯉のぼり巻き寿司♪子どもの日☆端午の節句」鯉のぼりにデコロール寿司はいかがですか?我が家の定番子どもの日料理です。具材アレンジしてもっと簡単にもできます。 材料:☆韓国海苔、☆白ゴマ入り酢飯、☆焼肉..
意外と簡単にできちゃう鯉のぼりの巻き寿司。見た目がとても可愛いので、子供もパクパク食べてくれそう♡
具材はアレンジ次第で自由自在。
生ものが苦手な子供の場合は、お肉でもOKです。親子で一緒に可愛くデコったら楽しいかもしれませんね♪
具材はアレンジ次第で自由自在。
生ものが苦手な子供の場合は、お肉でもOKです。親子で一緒に可愛くデコったら楽しいかもしれませんね♪
◆子どもの日☆鯉のぼり仕立ての手まり寿司 by るるこママ食べざかり 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「子どもの日☆鯉のぼり仕立ての手まり寿司」配置を工夫するだけで、子ども喜ぶ鯉のぼり寿司♪ネタ次第で、お父さんも満足です♡ 材料:炊きたてご飯、すし酢、白粒ゴマ..
楕円や長方形のお皿を鯉のぼりに見立てて作った可愛い手まり寿司。
ひとくちサイズの手まり寿司は、子供も食べやすいのでおすすめ♪子供の日のパーティーメニューとしても大人気ですよ!
色々な味を楽しめるので、好き嫌いの多い子供も安心ですね。
ひとくちサイズの手まり寿司は、子供も食べやすいのでおすすめ♪子供の日のパーティーメニューとしても大人気ですよ!
色々な味を楽しめるので、好き嫌いの多い子供も安心ですね。
◆子供の日の筍ご飯の焼きおにぎり by EGAmama 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「子供の日の筍ご飯の焼きおにぎり」旬の筍ご飯を焼きおにぎりにして、海苔のかぶとを乗っけました(笑) 材料:筍ご飯、海苔、ハムとチーズの春巻き風ぐるま..
端午の節句にちなんだたけのこご飯の焼きおにぎり。子供って、おにぎりだと食べてくれることが多いので、これは本当におすすめです。
海苔の兜を乗っけてひと工夫しているところがポイントですね♪
海苔の兜を乗っけてひと工夫しているところがポイントですね♪
◆こどもの日 春巻の皮のポテサラ包み by ponymoon 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「こどもの日 春巻の皮のポテサラ包み」揚げ焼きで油節約&カロリー減 材料:春巻の皮、水溶き小麦粉、好きな具材..
春巻きの皮でポテトサラダを包んで作った春巻きこどもの日バージョン!兜の形にアレンジされていますので、端午の節句にぴったりですね。
前日に余ったポテトサラダを使えば時短メニューに♡
具材は、ハムとチーズやベーコンとポテトなど何でもOKなので、子供の好きなものを包んで作ってみてください。
揚げ焼きするので、ヘルシーというのもポイントですよ♪
前日に余ったポテトサラダを使えば時短メニューに♡
具材は、ハムとチーズやベーコンとポテトなど何でもOKなので、子供の好きなものを包んで作ってみてください。
揚げ焼きするので、ヘルシーというのもポイントですよ♪
◆子供の日に♪鯉のぼりコロッケ♡ by スミスミたっくん 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「子供の日に♪鯉のぼりコロッケ♡」いつものコロッケにちょっと手を加えるだけでこんなに可愛い鯉のぼりが出来ちゃう♡ 材料:コロッケの具(ポテトやカボチャでも)、小麦粉、溶き卵..
子供の好きなコロッケも、鯉のぼりの形にアレンジ♪
ウロコは、スライスチーズ。目玉ははんぺんと海苔で出来ています。お弁当のおかずにもおすすめですよ!
ウロコは、スライスチーズ。目玉ははんぺんと海苔で出来ています。お弁当のおかずにもおすすめですよ!
◆端午の節句☆ロールサンドで鯉のぼり☆ by まゃたん 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「端午の節句☆ロールサンドで鯉のぼり☆」ロールサンドにデコしたら、こんなに可愛い鯉のぼりが出来ましたよ^^ 材料:サンドイッチ用食パン、デコペン、マーブルチョコ(なくてもOK)..
こどもの日の朝食メニューやお弁当におすすめ!こちらはロールサンドイッチで鯉のぼりを作りました。中の具材はなんでもOK!
ジャムサンドや卵、ハムチーズなど何でもクルクル巻いちゃいましょう。
仕上げは、デコペンを使ってウロコを描くだけ。簡単なのにとても可愛いですね。
ジャムサンドや卵、ハムチーズなど何でもクルクル巻いちゃいましょう。
仕上げは、デコペンを使ってウロコを描くだけ。簡単なのにとても可愛いですね。
◆こどもの日★鯉のぼりクッキー端午の節句 by 田んぼイネ 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「こどもの日★鯉のぼりクッキー端午の節句」目が二重になっている鯉のぼりは、少し大きめ♪鯉のぼりは型抜きではありませんので、お好きな大きさでどうぞ♪ 材料:薄力粉、バター、砂糖..
こどもの日のおやつにぴったりな手作りクッキーも鯉のぼりで♪
非常にシンプルな作り方なので、初心者さんでも安心です。
鯉のぼりは、型抜きではなく、長方形に形を整えてからしっぽの部分を三角に切り落とすだけなので簡単♡
クッキー生地作りが苦手な方は、クッキーミックス粉(あらかじめ調合してあるもの)を使って作ると手軽です。
非常にシンプルな作り方なので、初心者さんでも安心です。
鯉のぼりは、型抜きではなく、長方形に形を整えてからしっぽの部分を三角に切り落とすだけなので簡単♡
クッキー生地作りが苦手な方は、クッキーミックス粉(あらかじめ調合してあるもの)を使って作ると手軽です。
◆こどもの日♪簡単★鯉のぼりパイ★ by はーくま 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「こどもの日♪簡単★鯉のぼりパイ★」こどもの日に♪冷凍パイシートを使って簡単に出来ます♡見栄え、ボリュームGood★ホームパーティにオススメです(^^) 材料:冷凍パイシート、お好みのジャム、溶き卵..
難しそうに見えて意外と手間もかからず簡単に作れる鯉のぼりパイ。
冷凍パイシートを使用しているので、初心者でも失敗知らずです。
こちらはジャムを具材に使っていますが、おかずとして使いたいならミートパイにしたり、ベーコンポテトなどでもOK♡
簡単に出来るので子供と一緒に作ってみると楽しいと思います。
冷凍パイシートを使用しているので、初心者でも失敗知らずです。
こちらはジャムを具材に使っていますが、おかずとして使いたいならミートパイにしたり、ベーコンポテトなどでもOK♡
簡単に出来るので子供と一緒に作ってみると楽しいと思います。
◆子供の日に♪こいのぼりロール by マルサンパントリー 【クックパッド】 簡単おいしいみんなのレシピが304万品

「子供の日に♪こいのぼりロール」こどもの日にぴったり!!子供が喜ぶこいのぼりのロールケーキ♪ 材料:卵黄、砂糖(卵黄と混ぜる用)、牛乳..
お菓子作りが好きな方におすすめなのが、見た目も華やかな鯉のぼりのロールケーキ。
ロールケーキの生地は、普通のケーキを作るよりも意外と簡単なので初心者でもほとんど失敗なく出来ます。
ただし、メレンゲを作るのが大変なので、電動泡立て器があると便利です♡お好みのフルーツを入れて、盛り付けも可愛く華やかにしましょう!市販のケーキよりも頑張った分、ママの愛情がたっぷりですね。
ロールケーキの生地は、普通のケーキを作るよりも意外と簡単なので初心者でもほとんど失敗なく出来ます。
ただし、メレンゲを作るのが大変なので、電動泡立て器があると便利です♡お好みのフルーツを入れて、盛り付けも可愛く華やかにしましょう!市販のケーキよりも頑張った分、ママの愛情がたっぷりですね。
端午の節句は「菖蒲湯」に入る!
via www.photo-ac.com
よく端午の節句には「菖蒲湯」に入るというのを耳にしたことがありますが、これは一体なぜなのかご存知でしたか?
これは奈良時代から続く日本の古い習わしで、季節の変わり目である「午(五)」の日に、薬草を摘んだり、菖蒲を入れたお酒を飲んだりする「菖蒲の節句」というものが由来とされています。
菖蒲は、邪気を払う薬草であると考えられていたのです。
その後、江戸時代になり、菖蒲=尚武(勝負)と読み方が同じであることにあやかり、縁起を担いで武士が出陣の前に菖蒲湯に入っていたと言われています。
このような名残から、端午の節句に菖蒲湯に入ると縁起が良いとされているのですね。
実際に菖蒲には、鎮痛効果や血行促進、保湿効果などが期待出来ますので、体に良いものだと言えます。
菖蒲湯に使う菖蒲は、この季節になればスーパーなどでも売られていますので是非試してみてください。
使い方は、そのまま浴槽に入れて香りを楽しむだけでOKですが、長すぎる場合は、くるんと輪っか状にして使っても良いと思います。
これは奈良時代から続く日本の古い習わしで、季節の変わり目である「午(五)」の日に、薬草を摘んだり、菖蒲を入れたお酒を飲んだりする「菖蒲の節句」というものが由来とされています。
菖蒲は、邪気を払う薬草であると考えられていたのです。
その後、江戸時代になり、菖蒲=尚武(勝負)と読み方が同じであることにあやかり、縁起を担いで武士が出陣の前に菖蒲湯に入っていたと言われています。
このような名残から、端午の節句に菖蒲湯に入ると縁起が良いとされているのですね。
実際に菖蒲には、鎮痛効果や血行促進、保湿効果などが期待出来ますので、体に良いものだと言えます。
菖蒲湯に使う菖蒲は、この季節になればスーパーなどでも売られていますので是非試してみてください。
使い方は、そのまま浴槽に入れて香りを楽しむだけでOKですが、長すぎる場合は、くるんと輪っか状にして使っても良いと思います。
飾り付けはいつからいつまで?
via pixabay.com
端午の節句に欠かせないものと言えば、鎧兜と鯉のぼりの飾りですよね。
これらは、春のお彼岸が過ぎてから飾るのが一般的ですので、だいたい4月に入ってから飾るご家庭が多いようです。
片付ける時期には特に決まりはないようですが、湿気に弱い鎧兜の場合、お手入れが大変になりますので、出来れば梅雨入り前の5月中旬までには汚れを落として片付けるようにしましょう。
ちなみに、この飾り付けについてですが、災いを払う・縁起物の意味合いがありますので、飾るのを忘れていたからと端午の節句の前日に出すのはNG。
これを「一夜飾り」と言って、縁起が悪いとされています。
皆さん、忘れずにしっかりと飾るようにしてくださいね。
これらは、春のお彼岸が過ぎてから飾るのが一般的ですので、だいたい4月に入ってから飾るご家庭が多いようです。
片付ける時期には特に決まりはないようですが、湿気に弱い鎧兜の場合、お手入れが大変になりますので、出来れば梅雨入り前の5月中旬までには汚れを落として片付けるようにしましょう。
ちなみに、この飾り付けについてですが、災いを払う・縁起物の意味合いがありますので、飾るのを忘れていたからと端午の節句の前日に出すのはNG。
これを「一夜飾り」と言って、縁起が悪いとされています。
皆さん、忘れずにしっかりと飾るようにしてくださいね。
室内用こいのぼり大特集♡みんなはどうしてる?こどもの日のお祝い♪ – ikumama

5月5日はこどもの日、別名「端午の節句」とも呼ばれる日です。生まれてから初めて5月5日を迎える男の子にとってはこの日が初節句のお祝いの日に当たります。こどもの日といえば、風を受けて空を泳ぐこいのぼり。最近ではマンションに住んでいる方でも気軽に飾ることが出来るこいのぼりも沢山販売されています。今回はこどもの日のお祝いの仕方から、そんなオススメのこいのぼり飾りの情報まで、丸ごとご紹介していきましょう♪
まとめ
via www.photo-ac.com
いかがでしたか?
今回ご紹介した端午の節句だけでなく、節分や桃の節句など、段々と日本の古くからの季節行事が簡素化されてきている今。
本来の意味を知らない人も増えていますよね。私たちが、祖父母や両親から教わってきたように、これからは私たち自身が子供たちの世代へと受け継いでいかなければなりません。
是非皆さんも、改めてこれらの行事に目を向けて、子供と一緒に楽しみながら学んで下さいね♡
今回ご紹介した端午の節句だけでなく、節分や桃の節句など、段々と日本の古くからの季節行事が簡素化されてきている今。
本来の意味を知らない人も増えていますよね。私たちが、祖父母や両親から教わってきたように、これからは私たち自身が子供たちの世代へと受け継いでいかなければなりません。
是非皆さんも、改めてこれらの行事に目を向けて、子供と一緒に楽しみながら学んで下さいね♡

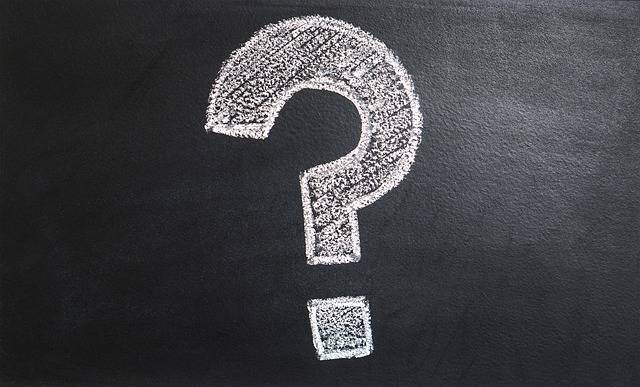





















旬のたけのこを入れて、子供の健やかな成長を願いましょう!
たけのこは、スーパーで売られている水煮タイプのものでOKなので簡単・時短ですね。